食べることは生きること。生きることは食べること。
毎日の暮らしをより豊かに、彩りあるものにしてくれるひとつが「食」。
自然と向き合う暮らしの中で、わたしたちは古くから知恵を巡らせ、その恩恵を食卓の中へ取り入れてきました。
春夏秋冬とめぐる四季折々の味を、一年を通じていつまでも味わっていたい。例えばそんな思いは、「発酵」という過程を通じた保存食を作りだし、わたしたちの日々の食卓にそっと寄り添っています。
なかでも長野県のご当地本である『信州の発酵食』(しなのき書房発行)には、彼らの身近にある発酵食との生活や知恵・食文化がありのままに綴られています。
信州が自然と育んできた丁寧な暮らし方から、生活のヒントを見つけてみませんか。
本から感じられるめくるめく季節の手しごと
はじめに語られるのは、移り変わる季節とともに感じられる四季の手しごと。信州の暮らしは四季の移ろいと共にせわしなく過ぎていくのです。
桜のつぼみがうっすらと見えはじめるころ、農家はせっせと味噌を仕込み、梅雨の時期となれば店先には漬物瓶が高く積み上げられる。緑茂るころ、夏野菜たちが食卓に顔を連ね、晩秋のころ、来たる冬に備え甘味をつけた菜っ葉たちは漬物桶で出番待ち。
この本から垣間見えるのは、今日は味噌漬け、明日は粕漬けと、手を変え「味」を変え漬物桶と向き合う姿。そして一年の恵みと向き合える、喜びに満ちた彼らの笑顔。
「今年は菜っ葉の味が濃いね。」
「随分と冷え込んだからね。」
そんな会話を交わしながら、漬物桶に手を入れる夫婦の姿が浮かんできます。
「発酵食」との暮らし方
長野県民は発酵という方法をうまく食生活にとりいれ、「発酵食」文化を構築してきた、と『信州の発酵食』は語っています。
発酵食の代表といえば、味噌。
長野県の味噌は3年熟成させた長期熟成のものが主流のようで、全国的にも信州味噌の美味しさは知られていますね。
味噌蔵それぞれが、代々一生懸命味噌を作ってきたからこそ、信州の暮らしにはさまざまな味噌料理が根付いています。
『信州の発酵食』に紹介されている味噌をつかったレシピからは、毎日の味噌づかいのヒントが描かれています。まるで田舎のおばあちゃんがこっそり教えてくれた秘密のレシピのよう。
それから酒。
酒づくりに大切なのは寒い気候と米と水です。3つの条件がうまく重なることに加え、昔から酒づくりを続けてきたことがおいしい酒を生み出しているのだとか。なぜなら古い蔵にはその蔵独自の酵母が棲みついており、いわゆるその「家つき酵母」が良い発酵しごとを担っているからなのだそうです。
そして信州の発酵食といえば、やはり漬物。
ふきの糠漬け、大根の麹漬けなど、その種類は挙げればきりがないほど。ページをめくるたびに出会う新しい漬物たちに、どんな味なのだろうか、どう食してみようか、今年は自分で漬けてみようかと、まるで頭の中は漬物に思いを馳せる旅に連れて行かれたよう。
地菜といって、地域ごとに異なる菜っ葉を漬けた漬物があるようで、次の旅行は「地菜を巡る旅」にしてみるのも、その地域の暮らしが見える気がして楽しそうではないですか?
信州が長い時間をかけて構築してきた食文化である「発酵食」。
その時期にだけ採れる食材を、その時期にできる方法で保存し、時間をかけて食す。自然と共に歩むその丁寧な暮らし方こそが、本当の豊かさと言えるのかもしれません。
信州の暮らし方をありのままに教えてくれる『信州の発酵食』は、
「お疲れ様。これ食べてちょっと休みなさいよ。」
と優しく語りかけてくれるおばあちゃんのよう。
そんな飾らない優しさと愛情が、まるで漬物のように体の奥深くまでホッと染み渡るのです。

『信州の発酵食』
発行:しなのき書房、著:小泉武夫/横山タカ子
長寿県信州の秘密は発酵食にあり! 春夏秋冬、信州の1年は自然の恵みとともに そして発酵食とともにめぐります。 発酵食とは、自然と向き合い 暮らすなかで生まれた人智が詰まった 信州が誇る〝豊かさ〟です。長寿のための発酵食レシピも掲載。
- 648円(税込)
- 購入はこちらから
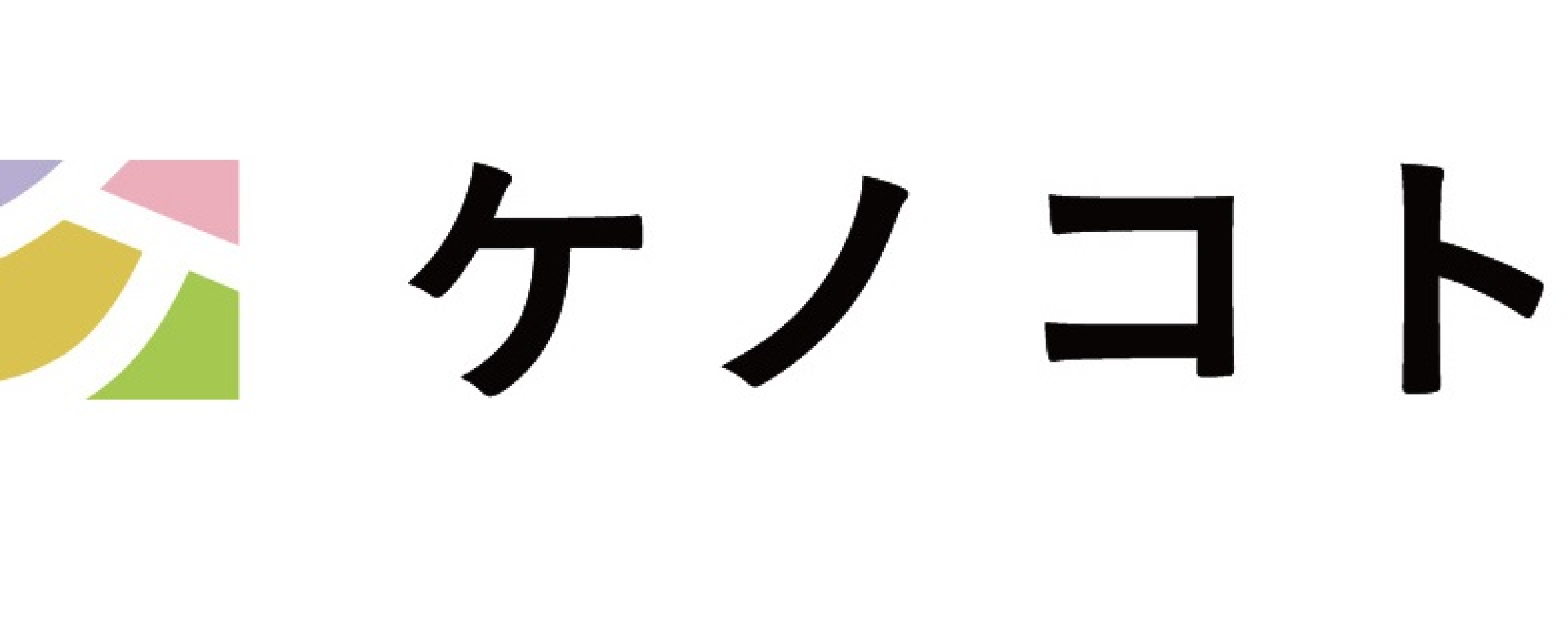
-
「ケノコト」
毎日の何気ない暮らしこそ大事なことがたくさん。ケノコトは日常と食をより楽しくするメディアです。ケノコトの“ケ”は、「食べる」や「糧」といった食(け)のことと「ハレとケ」のケ=「日常」を表しています。ケノコトのコンセプトは“ココのある暮らし”。ココとは個々(1人1人)、此所(色んな場所で)、小幸(小さな幸せ)。日常を彩るちょっとした幸せ。そんな瞬間が生まれるきっかけをつくること、それが「ケノコト」の役割です。
―ご当地本からひもとく「地域のコト」―
第1回『信州の発酵食』からみえる
“丁寧な暮らし方のヒント”
第2回『続・名古屋の喫茶店』からみえる
名古屋人の喫茶愛と足し算文化 >>
第3回『京都珍百景』で知る、
「珍」京都のススメ >>
第4回『オキナワグラフ』で知る、
ガイドブックに載らない沖縄の姿 >>
第5回『下仁田ねぎの本』からみえる、
歴史と地域に根づく食材の力 >>
第6回『家庭でつくる 沖縄の漬物とおやつ』から感じる、
おばぁのぬくもりと島の飾らない家庭の味 >>










